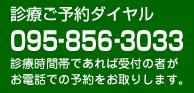コラム「LOUNGE-11月号」 ―最小限の処方で最大の効果を上げること―
(2010年11月9日掲載) 一言で申しますと、その時の状態に合った処方であることに尽きると思います。治療初期には、少量かつ単剤を原則として開始し、賦活症候群※などに注意し、できるだけ早い時期に適量の処方内容にすることです。これは重症度に応じた初期からの多剤かつ大量の投薬を否定するものではありません。
では、「状態に合う」とはどのようなことなのでしょうか。たとえば、うつ病なのか不安障害なのか、うつ病であれば躁状態を伴うのか否か、不安障害であれば状況の関与があるのか否かなどのアルゴリズムに従い、初期の見立てを確かなものにしておくことが肝要です。そうすると自ずと、どの薬剤をどの程度の量で投与すべきかが決まります。
最初の薬でうまくいくケースは約半数ほどで、薬を変えながら経過をみることで適切な処方内容になることもあります。心療内科で用いる薬の多くは、理論上の効能や副作用だけでなく、その方の薬との相性を考慮せねばならないからです。なぜその処方内容になったのかについては理由がありますので、面接ではその服用感について都度医師と話し合うことが重要です。身体とこころの状態は治療を始めてから、時間とともに変化していきます。漫然と同じ処方内容を続けることは原則慎まねばなりません。もちろん、心身の状態と薬とがホメオスタシス(恒常性)を保っている状態では処方内容に変化をもたせないこともあります。
それでは、症状が改善された後はどの程度服薬を維持したほうがよいのでしょうか。ケースバイケースでありますが、たとえば、うつ病を含むこころの疾患では、他の身体疾患のように生体の異常を視覚的に確認することが難しく、病気が改善した状態を客観的に捉えることが困難です。そこで最新の理論と経験に基づき、その方に合った治療プランを提案することになるのですが、最近では脳神経ネットワークの損傷と抗うつ薬による修復の視点から、症状が改善された後も、しばらくの間服用を続けることが、再発・再燃に移行しないと言われています。一見遠回りのようにみえますが、再燃を繰り返して薬物の量が増えていく(多剤・大量処方)ことを防げるのです。
| ※賦活症候群: | 抗うつ剤の服用初期に、不眠、不安が出現することがあり、それが抗うつ剤によるものか、原病の悪化なのかの鑑別を要する。 |
―待合室で読める本から―
「うつと気分障害」(幻冬舎新書) 岡田 尊司 著気分障害を抱えた方が社会でうまく活躍していくために、生活習慣やライフスタイルの問題、考え方の偏りに起因する面に気づき、その対処法を理解するヒントを与えてくれます。 「わたしは働くうつウーマン」(小学館) 安部 結貴 著
読み終えた後、「うつでも大丈夫」と思える勇気づけられる内容です。マンガですので気分が落ち込んでいるときにも読めます。 「それってほんとに“うつ”?」(講談社) 吉野 聡 著
“うつ”と名のつくものには様々な病態があり、職場で問題となりやすい現代型うつ病やパーソナリティ障害について、それぞれの病態に適した治療法があることを教えてくれます。